


ヴィクトリア時代の女性にとって、服喪の期間はさぞたいへんで、辛かったことでしょう。
服喪の期間が長い。亡くなったのが
夫であれば 2年(半)
親、または子 1年
兄弟姉妹 半年
伯父、伯母 3ヶ月
いとこ 6週間男性は喪章をつけるだけでよかったのですが、女性は全身、黒づくめでした。
服喪期間に結婚する場合、ウェディングドレスは黒か灰色(うわ〜)。
自分の子供の結婚式に出席する未亡人は、濃い赤のドレスが認められました(なぜ?)
正式な喪が1年間。さらにやや軽い喪が1年間。服喪期間の1年目は、未亡人は社会とまったく縁を切った生活を強いられました。
あらゆる招待は断らなけれならず、みとめられていたのは、近親者を訪問したり、結婚式や洗礼式などの教会行事のみでした。
一応2年間、ということになっていますが、さらに半年ほどは準喪服を着ているのが普通でした。
やっと1年過ぎたと思ったら、またすぐ別の近親者や政府要人、王族が亡くなって、喪服に逆戻り、ということもありました。
妻は夫の近親者が亡くなった場合にも、喪服を着なければなりませんでした。2年目からは、正喪服をやめて、もう少しお洒落な黒服に、黒い宝石類をつけました。
ジェット、アメジスト、真珠、ダイヤモンドなどが認められていました。急に喪に服す事になると、大変な出費がかかりました。
1年分の衣装、バッグ、靴、傘などの小物を黒でそろえなければならないうえに、大きなお屋敷になると、使用人たちにも喪服を着せなければなりません。
そんなわけで御婦人がたは手持ちの衣装を黒く染めて、喪服にしたのです。

どちらもビクトリア時代に大流行でした。
これにホームズの産みの親、コナン・ドイルが夢中だったのは有名ですね。交霊会は、霊との交信が目的でおこなわれる会で、霊媒を介してあの世の霊と話をしたり、あの世からメッセージを受けたり、霊そのものを呼び出して質問をしたりするものです。
たとえば、こっくりさんや、イタコの口寄せなども、交霊会になります。降霊会は、霊現象を求めるもので、こちらは交信が目的ではありません。
霊の手型をとるとか、ポルターガイストを見るとか、心霊写真を撮るとか、現象そのものが目的になります。

踏み車、というものにはいろいろな形がありますが、要するに、水車は水で、風車は風で動かすのに対し、踏み車は足で踏むことで回転させる車輪です。
用水路などにある、小さな踏み車などを見たことのあるかたもいるでしょう。
ここで説明する踏み車は、ビクトリア時代の監獄に設置されたものです。
かわいく言えば、<ルームランナー拷問バージョン@監獄❼>です。
うーん。やっぱり殺伐とした匂いは消えないか。踏み車は1817年にBrixton監獄に初めて設置されました。
もちろん、水をくみあげるため、という実用的な踏み車もありましたが、ほとんどが拷問目的でした。
その証拠に、風圧を使った調節弁がつけられていて、回転をきつくして、罪人たちがいくらがんばって踏んでも、なかなか回らないようにすることができるようになっています。
1分間に2回転する巨大な車輪の上を15分間歩き、ベルが鳴ると次の人と交替する、というローテーションで、監獄によって回転数は違いましたが、一万歩以上歩くことになるのは、どこもかわりありませんでした。
しかも、これは車輪の上を歩くわけですから、平面を歩くのでなく、永遠に続く階段をのぼっているのと同じです。
別名。「到達点のない階段」「永遠への階段」「ジャック・ザ・スリッパー」「人生の車輪」
ロクな食事も与えられず、こんな苦行をさせられてはたまりません。
当然、わざと足に傷をつけたり、仮病を装おったりして、さぼる人間が続出しました。それにしても、なんのためにこんなものを作ったのか。
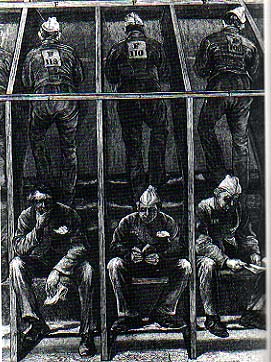

ビクトリア時代の貴婦人は、「何もしない」ことが求められました。
自分でちょっとした仕事をすれば、「はしたない」とみなされたのです。
そんなわけで、レディの身の回りの世話をするために、侍女が雇われました。
この<身の回りの世話>というのは、着替えをさせ、髪をとかし、身体を洗い、
寝かし付けるという、ほとんど介護に近いものでした。
なにしろ、レディたるもの、何もしてはいけないので、赤ん坊と同じなのです。侍女は特権として、女主人のおさがりの服をもらうことができました。
女性の使用人の中で、もっとも位が高かったのです。使用人には階級がありました。
男性使用人を監督するのが執事。
女性使用人を監督するのが家政婦。
執事と家政婦が、使用人の採用、免職も決定しました。
侍女は女性使用人の中でも別格で、執事、家政婦と並ぶ、上級使用人とみなされました。
ですから、女性使用人の中で唯一、家政婦の監督を受けませんでしたし、家政婦からクビを言い渡されることもありませんでした。
そして、ほかの使用人たちが使用人の部屋で食事をする間、侍女は家政婦、執事とともに、家政婦の部屋(パントリー)で食事をとることを許されました。
けれども、侍女は一般的に若い女性ということになっていたので、歳をとると、年齢だけを理由にクビになることもありえたのです。
できれば侍女はフランス人のほうがいい、と言われていました。
が、それがムリな場合は、フランス風に名前を呼ぶことで、雰囲気を出したらしい。
例 ジェーンをジャネットと呼ぶ。

現代でいう遊園地、テーマパークのようなものが、当時のロンドンにはたくさんありました。
プレジャーガーデンズと呼ばれています。
クリモーン庭園はチェルシーの「スタジアム」というプレジャーガーデンズを前身として、1845年に開園しました。
ディズニーランドのように、きれいな遊歩道、楼閣、喫茶店がもうけられ、舞踏会、サーカス、芝居小屋、ポニー競馬などの娯楽が豊富でした。
特に有名だったのが、気球ショーと、午後11時半の花火ショーです。
花火の音に相当苦情があったようですが、大人気だったので、無視されました。
最初は健全な遊園地だったここも、のちにはロンドン一のいかがわしい場所となり、娼婦などが集まる、悪の巣窟になってしまいました。
1874年5月に「空飛ぶ男(フライングマン)」が気球ショーで失敗し、墜死したのがきっかけで、ついに閉園においこまれました。

名刺くばりは、上流階級の人々にとって大事な仕事でした。
いろいろな人とのコネが、とっても重要だったからです。
夫の名刺、夫人の名刺が、別々に作られました。
お近づきになりたい家には、夫の名刺を2枚と、夫人の名刺を1枚届けます。
夫の名刺と夫人の名刺を、女主人に。
夫の名刺を、主人に。
未婚の娘がいる場合は、夫人の名刺の下に書き添えました。
未亡人は黒縁の名刺を作りました。
名刺を受け取ると、盆の上に並べて玄関先のテーブルにおいたり、暖炉のマントルピースの上に並べたりしました。
この家はこんな人たちとおつきあいがある、と、お客さんに見せつけるわけです。
当然、なんとか伯爵、なんとか公爵、という、派手な名刺を、いちばん目立つように飾りました。
そりゃ〜、わたしでもそうしますわ。

袖のかわりにケープのついた、婦人用のコートというかマントです。
ノースリーブのコートの上に、長めのケープ(小さなマントのような肩にはおる布)がついたものです。
「銀河鉄道999」のメーテルが着ているコートの袖がないもの、という説明がいちばんわかりやすいかも。(ちょっと違うけど)

