

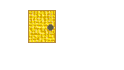
時期的に、またそろそろ進路相談のメールが届きそうなので、掲示板のとある質問に対するわたしの回答と、その補足をのせることにしました。
質問者は、将来は好きな英語を生かした仕事をしたい、特に、洋楽の訳詞をしてみたい、というご希望の高校生です。
で、わたしのお返事がこんな感じ。----------------------------------------------------------------------------
中学、高校生時代、わたしは洋楽ファンで、特にRick Springfieldが大好きで、「絶対、結婚する」などとよまいごとを言っておりました。
洋楽アーティストに会って、たくさんおしゃべりできる小林克也さんがうらやましくて、将来、あんなふうになれたらいいな、と憧れていましたよ。
中学生程度の英語力では、歌詞の意味がわからないので、全部、ノートに書き写して、一生懸命に和訳していました。
あれでムダな単語をいっぱい覚えましたね〜。affairとかさ。
いつかRickに会うんだ、と、「続基礎英語」もかかさず聞きました。
オーストラリア(Rickの故郷)や、カリフォルニア(いま住んでるところ)に行くんだ、とガイドブックを読みまくりました。
あれがいまのわたしを作ったんでしょうかね。
なぜ、洋楽のほうではなくミステリのほうに進んだかというと、おそらくRickが結婚しちまって、どーでもよくなったからでしょう。
考えてみると、「洋楽関係の仕事がしたい!」「ミステリの翻訳がしたい!」というエネルギーは、それが好きである、という一点にあったと思います。
でないと、なかなか続かない気がするな〜。
お金もうけにはむかないしさ。
当時、ライナーノーツを書いたり、インタビューしたりしていた人は、英語力よりも音楽に詳しいことが優先されていました。
専門分野に強いことは、大きな武器になりますよ。----------------------------------------------------------------------------
当時のヒットソングの歌詞をコクヨの大学ノートに書き写して、必死に訳していたおかげで、おそらくは校内でいちばんムダなスラングを覚えていたわたしは、当然、英語の成績もよくなり、また、英語が好きになっていました。
実際、わたしが大学生になったころはDJになりたい、などという夢もあったのですが、バカなわたしは、自分が年に4回風邪をひき、インフルエンザももれなく大当たりという、超虚弱気管支の持ち主であることを忘れておりました。
塾で講師のバイトをして、思い知りましたね。のどを使った職業は無理だと。
おまけに、わたしはあまり社交的な性格ではなく、ほとんどひきこもりですから、知らない人とあれこれおしゃべりをする、というのがなかなかストレスなのです。
むかないだろ。インタビュアーには。というわけで、幼いころからの趣味、読書に関係する仕事をしたい、と完全に心をかためた時に、「読書プラス英語」で翻訳という職業が出てきたわけです。
英語が好き、というだけなら、言語学や音声学を大学院に進んで研究すればいいわけで、好きな英語を役立てた仕事をしたいのであれば、英語プラス何かの「何か」が大事になってくると思います。
翻訳なら「本」とか「外国の文化について知ること」とか「文章をいじくること」とか。
通訳なら「海外、日本文化について知ること」とか「大勢の人と会うこと」とか「旅行が好き」とか。
その「何か」がないと、進路をきめるのは難しいのでは。
「英語」プラス「料理」とか、「英語」プラス「生け花」とか、「英語」プラス「音楽」とか、「英語」プラス「映画」とか、「英語」プラス「お買い物」とか。
その「何か」を見つける期間が学生時代(小、中、高もふくめて)なのだと思いますよ。
で、やりたいことが見つかった時のために、英語の勉強も続けてくださいまし。----------------------------------------------------------------------------
しかし、こう書いたあとで、うーむ、ちょっとたりなかったか、と思いました。特に文芸翻訳の場合。(ほかのジャンルについては、よくわからないので)
言語はいろいろありますが、まあ、わかりやすくするために、英語から日本語に訳す、としましょう。
で、英和の文芸翻訳の場合は、「英語が大好き」な人よりも、「英語ができて、日本語が大好き」な人のほうがむいています。
なぜならば、作業のほとんどが日本語をいじくることですし、商品も日本語訳だからです。
たとえば、「sapphire」という単語があるとします。これを「サファイア」とするよりも、「青玉」、「碧玉」、「瑠璃」などと表記して「サファイア」とルビをふったほうがきれいかな、とか。(ひらがなでルビをふると、もっとレトロな感じですてきかも、とか)
グレーも「灰色」「鼠色」「ねずみ色」ばかりでなく、「鈍色(にびいろ)」とか、「薄墨色」とかのほうが感じがでるかな、とか。
どちらかといえば、この日本語探しに頭をかきむしっている時間のほうがずっと長いので、この作業を楽しめる人のほうが、外国語から日本語に訳す文芸翻訳にむいています。
三人の師の教え もともと受け売りばかりのこのコーナー。
いまさら<師の教え>もないもんだ、という気がしますが、そういえばこんなことも言われたな〜、ということを多少思い出しました。
というわけで、今回は純度100%の受け売りです。(その分、わたしの言葉よりもありがたみはあるかも)例の厳しい老師は、わたしたちが間違えるたびに、「どうしてそういう誤訳をする!」と、そりゃーもう恐ろしい顔でお怒りになるのでした。「原文どおりに訳しなさい!」
しかし、叱られれば委縮するのが若い(当時)女の子というもので、わたしたちはひたすら怒られまい、叱られまいと、やけに生真面目に訳すようになってしまいました。
訳としては間違いのない正確な訳だけれども、なんのおもしろみもない無味乾燥な、英文解釈に近い、無難な日本語ばかり作るようになったわけです。
だけど、そんなもんは翻訳とは言わんわな。
当然、それはそれで怒られます。「女子大の優等生の訳だ。これは最低の訳だ!」
だって、わっかんないよ〜。
そういう状態がしばらく続いて、のっぺら〜とした答案ばかり読まされた老師は、ついに堪忍袋の緒を切りました。
「間違えてもいいのです! おもしろく訳しなさい!」
えー。言ってることが全然違うじゃん。先生のバカ。(いやいや、ほら、若い女の子だからね。生意気なことも考えるわけですよ・・ごめんなさい、先生。許して)
けれども、妙にインパクトのあったこの言葉は、それから長くわたしの脳のすみっこにくすぶり続けることになりました。こんなわたしもようやくデビューしたものの、いまひとつ自分のやりかたに自信が持てず、こんなにクセの強い訳しかたでいいのだろうか、いまだに担当さんに誤訳をなおされてばっかだしさ、と日々悩んでいた頃のこと。
担当編集者某氏がにこにこしながら言いました。
「正確でつまらない訳より、多少間違いがあってもおもしろい訳のほうがいいんですよ」
「・・なんで?」
「編集にはおもしろくできませんから」
「?」
つまり、編集者は原稿の間違いをなおすことはできるけれども、原稿に手を入れておもしろくすることはできない。
だから<間違いの少ない平凡な原稿>と<多少間違いはあってもおもしろい原稿>は、編集や校閲のチェックを受けたあとには、<間違いのほとんどない平凡な原稿>と<間違いのほとんどないおもしろい原稿>になる。
「委縮して無難にやるより、多少大胆にやってもらったほうがいいんです。それでやりすぎていたら、やりすぎですと編集者が言いますし、間違えていればなおしてもらえばいいんですから」
まあ、もちろん限度はありますけどね、とばっちり釘はさされましたが。しかし、この<大胆>という言葉はおおざっぱすぎて、具体的にはどういうことだ、と迷ってしまいますね。
そのヒントをくれたのが、師匠でした ・・酒を飲みながら。
酔っぱらっていた師匠の話をまとめるとこんな感じになります。
訳者にはいろいろな特権がある、と。
まず、キャラクターを設定する権利。これは当然ですよね。キャラは訳者が原書から読み取ったイメージできめるしかありませんし、キャラ設定が決まらなければ、セリフも決められませんから。
そして、訳語の選択。時には、たとえ原語から離れても、作者の意図、作品のねらいを伝えることを優先させるために大胆な訳をしたり。また、時には、オリジナルの訳語を創造したり。
もうひとつ。あいまいな記述に関しては、自分なりに解釈、決定してしまうこと。簡単な例でいちばんよくあるのが、「このブラザーってのは、兄と弟のどっちなんだ!」ですね。それはもう訳者が「兄ってことにしておこう」と決めちゃっていいと。
「要はおもしろく、わかりやすく訳せばいいんだよ。そのために大胆な発想だの、臨機応変な対処だのが必要になるだけで」
師匠のお言葉は結局、老師のお言葉につながります。
「原文どおりに訳しなさい!」
要するに老師は<原文の形を忠実に日本語に置きかえなさい>という意味ではなく、<原文が伝えようとしていることを、いちばんふさわしい日本語で伝えなさい>という意味で<原文どおり>とおっしゃっていたわけですね。ここまでの話から「そーか。びびるなってことだな。大胆にがんがんやっちゃえ」と思わないでくださいね。
この話を参考にしていのは、翻訳の勉強をある程度続けて、それなりの実力をつけた人だけです。
初心者はだめ〜。
ここからはまた老師の受け売りになりますが、翻訳の勉強をはじめたばかりの人というのは、びっくりするほど大胆な訳をします。
ただしその大胆さは、暴発というか、逸脱というか、そんなことは原文に書かれていないよ、という困った大胆さなのです。
勉強をはじめたばかりの人は、まずはなるべく原文に忠実な、暴れていない訳を作ることをこころがける必要があります。
そして、形がだんだんきれいに矯正されてくると、今度は「こんな平凡な英文解釈じゃ、自分だって訳していてつまらないし、読者にとってもおもしろくないはずだ。もっと魅力的な訳文を作りたい」と思うようになります。
実は、そこからが翻訳の勉強なのです。それまでは、スタートラインに立つまでの準備期間のようなものです。
この段階にはいった翻訳家のひよこたちは、翻訳でいちばん難しい<さじ加減>というものに悩み、苦しむようになります。
おもしろくしようとすると、逸脱になってしまうのではないか。
どの程度まで大胆にやっていいのだろう。
どこまで原文の形に忠実に従うべきなのだろう。と、迷って、固くなり過ぎて、思いきってのびのびとした訳ができずにいるあなた。
三人の師の話を参考に、肩の力を抜いて、楽しく訳してくださいな。
何冊か訳すと、「ここまではセーフ!」というのが、だんだんわかってきますしね〜。
さじかげん 最初に教わった老師に「原文どおりに!」と言われ続けたわたしは、とにかく原文に忠実に訳して、その中で表現を工夫しようと懸命になっていましたが、そうすると、ただ単語をいじくりまわした、工夫というよりも、小手先の小賢しい小細工になってしまうのでした。
単語や表現のみがひとり歩きを始めて、工夫したつもりの箇所が妙に浮いてしまったり。
凝った表現にしたつもりが、<そんなことは書かれていない>訳になってしまったり。
うーむ。さじかげんってむつかしい。
そんなわたしが師匠のもとに通い始めて、師匠の訳しかたにふれるようになって、約一年。
「見えた!」
ついに「原文にとらわれずに、原文どおりに訳す」方法のとっかかりをつかんだ気がして、ある日、酒を飲んでいる師匠に言いました。
「せんせー。最近、やっとわかったんですけど、わたし、むかしは英語の文を直接、日本語に変換しようとしてたので、くだらないこまこましたことに悩んでたんですよ。でも、このごろは英語の文を読んでから、まず頭の中に映像を浮かべて、その映像を日本語で表現するって方法に切り替えたので、原文と訳文の単語が逐一イコールになっていなくても、意味だけは原文どおりって訳しかたが自然にできるようになってきたんですよ」
「それは普通じゃないの?」
さらっと言われて、あたしはそれに気づくまで6年も7年もかかったんだよ、とちょっと落ちこみましたが、一応、正しいアプローチであることは保証されたわけで、以来、そうこころがけるようになりました。
すると、心眼が開眼したのでしょうか。それまではつとめて映像を思い浮かべなければならなかったのに、いつしか英文→映像→日本語訳が無意識のうちに瞬時におこなわれるようになっていたのです。
条件反射ってすごいわ〜。ところで、「でも、登場人物の心理描写やひとりごとばっかりで映像にならない文もあるじゃん」という場合もありますね。
それから、「なんでいきなりここにこんな文がはいってくるわけ?」と、一見、唐突な文がはいってきたりすると、映像化もへったくれもありませんわね。
そういう場合はどうするか。
作者の眼になって見るのです。
作者はどんなつもりで、この文を書いているのか。
なぜ登場人物にこんな行動をさせたり、こんな台詞を言わせたりしているのか。
という、作者の意図をくみとり、「では、その作者の意図を読者に伝えるには、どんな日本語にすればよいか」と考えて、訳を作りあげます。
こういう場合、原文と日本語が全然、違うものになってしまうことがあるのですが、作者が読者に対して「こういうことを伝えたい」「こういう仕掛けで驚かせたい」という目的を優先させることが、結局は誠実な翻訳であると、わたしは思います。
何も考えずに原文をそのまま日本語に変換するほうがラクだもん。ところで、<行間をくみとって訳したつもり>が<そんなことは書かれていない訳>になってしまう、という事故はどうすれば防げるのか、というのが、勉強中には難しい課題ですね。
一応、おおざっぱな目安としては、<おぎなう>のではなく<いいかえ>に徹することで、それは防げると思います。
たとえば「涙が流れた」という文があるとします。
その光景をぱっと頭に浮かべて、それをいろいろな表現でいいかえるのが工夫ですね。
「涙が溢れた」「涙がこぼれた」「泪が頬をつたった」等々。
その光景を頭に浮かべると、自分も<読者>である以上、感想や解釈を抱くのは普通です。
「悲しいんだな」「悔しいんだな」「怒っているんだな」等々。
これをおぎなってしまうと、<そんなことは書かれていない訳>になってしまうのです。
訳者が「悔し涙」とかやってしまうと、訳を読んだ読者がそれ以外の解釈をできなくなってしまいますよね。
まあ、訳者も人間である以上、自分の感想、解釈、バイアスを完全に排除することは不可能なのですが、なるべく余計なものはおぎなわないように、と気をつかうことで、<そんなことは書かれていない訳>になる確率を低くすることはできます。
