
パーティーがあると、ドレスを買える。ちょっと高級な美容院にも大手を振って行くことができる。うれしーい。
今年は季節感ただようドレスを新調した。銀色のレース地にスパンコールが散って、きらきら光るワンピース。
テーマは秋刀魚よ。さんま。
脂がのってブリブリしてるところまでそっくりだね、という妹の言葉は無視する。やかましい。これでも、だいぶんやせたんだからね。
さて、三年前に鮎川賞の受賞パーティーに招待していただいた時には、ガチガチに緊張していて、食べ物はなにひとつノドを通らず、写真を撮ることもできなかったのだが、今年のわたしは違った。
「ケーキよ、ケーキ。食べなきゃ損よ」とかたっぱしからお菓子を荒しまわり、あげくにクレープまで作らせて食べた。
写真も枚数こそ少ないけれど、いろいろな作家さんたちに「すみませーん」と声をかけて、ツーショットで撮ってもらった。
その時は、「ふふふ。あたしもやっと場慣れしたのね」とほくそえんでいたのだが、しかし、この行動パターンは、よくよく考えれば、単におばさん化が進んで、ずうずうしくなっただけではないか。
ううむ。これはいかん。少し、おしとやかにキャラ修正しよう。
そう思っているところに、慶徳さんが通りかかった。
わたしのホームページを見てくださっているという、実に感心なお嬢さんをまじえて、以前、ここのこぼれ話に書いた、彼がホームズ時代のカレンダーをパソコンでささっと作ったというネタの話になった。
すると慶徳さんは、こんな生意気なことを言い出した。「あんなものは紙とえんぴつがあれば、子供にでもできます」
「あたしはできないもん」
「一日あれば、暗算でもできますが」
「・・じゃあ、なにかい。紙とえんぴつを使うってのは、レベルの低い話かい」
「はい」
きっぱり言うなー!
「ええい、どうしてそうかわいげがないんだ!」おまえはー、おまえはー、とどつき回すわたしはとっくに、鬼のようなおばさんなのだった。
いいです。もう、この路線で行きます。後日。掲示板に匿名希望さんの書き込みが。
> 「一日あれば、暗算でもできますが」
一日もいりません。
「曜日の知りたいのが一日だけなら、暗算だけですませてもよいのですが」
と言ったんです。
などというとまたどつかれるのだろうか。むかつく。ぷんぷん。
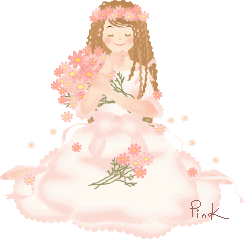
招待状をもらった段階では、単純に喜んでいた。ふっふっふ。有栖川さんと山口雅也さんにサインをもらって、作家さんたちの写真を撮りまくって・・と、妄想は激しくふくらむばかり。
が、しかし。5日前に初めての訳書が出て、すっかりナーバスになっていたわたしは風邪をひいてしまい、パーティー当日までクスリ漬けで、ふらふらだった。
倒れるかもしれん。
ホテルエドモントにたどりつくまでに、何度もめまいを起こしながら、真剣にそう思った。
ロビーにはいった瞬間に、戸川さんとばったりお会いする。「初めての本が出た感想は?」ときかれて、思わず「見捨てないでくださいー、次、がんばりますからー」と正直な感想を言ってしまう。
二階の会場前には、著明なかたがたがちらほらと集まりだしていた。ゲストは全員、受付で名札をもらっているので、まるっきり新参者のわたしにも、眼の前を通過する人が誰なのか、すぐにわかる。たまーに名札なしでもわかる人がいるけれど。
きょろきょろしていたわたしの前を颯爽と横切った人がいた。島田荘司さんだ。
か、かっこいー❼
ナマで見ると、なんて素敵な人なの。
やがて、綾辻さん、有栖川さん、京極さん、北村さんと、会場前はますます華やかになってきた。ああっ、写真撮りたい。
でもー、でもー、でもー、いまいち勇気が。
倉知さんや、大倉崇裕さんとおしゃべりしている間に、6時になった。扉が開くと、中からまばゆい光が。金屏風といい、立食バイキングといい、披露宴の二次会風景のよう。
やがて、鮎川哲也賞、創元推理短編賞、創元推理評論賞、それぞれについて、審査員のかたがたにより、選評がのべられた。
鮎川哲也賞は有栖川さん。最終選考に残った作品、ひとつひとつについて、丁寧にコメントされるのだが、全然メモを見ないで、しかも引用をたくさんいれてらっしゃることに、まずびっくりした。あの記憶力がうらやましい。
創元推理短編賞は北村さん。いきなり野球の話のつかみからはいって、笑わせてくださる。さすがだ。
創元推理評論賞は巽さん。なかなかシニカルな鋭いことを、ずばずばコメントされているのに、いちばん笑いが多かった。うちの大学に、似た雰囲気の人気教授がいたなー。
そして鮎川哲也賞を受賞された飛鳥部勝則さん登場。賞や花束の贈呈がつつがなく終わり、ご本人の挨拶となる。とてつもなく明るいお話で、作品を拝読する前にファンになってしまった。うん、おもしろい人だ。
こうして贈呈式が終わると、そのままパーティーに突入。しかし、会場にいる人でわたしが実際に知っているのは、ほとんど全員、東京創元社のかたばかり。
どうしよう、どうしよう、と思っていたら、運良く浅羽さんに遭遇した。拙訳についてあたたかい講評をいただく。翻訳家の柿沼さんや、大津波さんにも、「あら、新人さん? 地獄へようこそー」「一万枚訳せば、一人前になれるっていうから」「あせらないでがんばってね」と優しく励ましていただいた。ああ、お姉さまたち、ありがとう。
さて、すっかり気が楽になったわたしは、有栖川さんと山口さんのご著書を抱きしめて、サインをもらおうとうろついていた。ここで、またまた浅羽さんと会ったので、おふたりに紹介してもらう。
有栖川さんは、ファンレターを出したことを覚えていてくれた。山口さんにも名刺をもらっちゃったから、いつかお手紙だそうっと。
お目当てのサインを手にいれて、ほくほくして歩いていたら、編集部の伊藤さんと、鯨統一郎さんに会った。
「わたしファンなんです。<邪馬台国はどこですか?>の次の作品、楽しみにしてますね」と、しばらくお喋りをして、別れてしまうと、またひとりぼっちになってしまった。うーむ、こういう時、新米はつらい。誰かヒマそうな知り合いはいないかしら・・。あっ、いたっ!
わたしは食事中の慶徳さんを捕獲した。ほっほっほっ、もう逃がさなくてよ。
それからはずっと小判鮫のように、彼にくっついていたので、作家、評論家のかたがたとたくさんお話ができた。<猿来たりなば>の解説を書いてくださった森英俊さんは、原書の提供者でもあるので、翻訳のできについて問いつめたところ、「雰囲気でてると思いましたよ」とのこと。よかったー。
そろそろお開きという段になって、ふと写真を一枚も撮っていないことを思い出した。 「ねー、慶徳さん。島田荘司さんの写真、撮りたいなー」・・なんてわがままな女だ。ごめんね、慶徳さん。
それでも彼のおかげで、島田さんとツーショットで写真を撮ってもらえたのでした。その後、両手でしっかり握手までしてもらう。うっとり。
パーティーのあと、会場の出口で、飛鳥部さんの受賞作<殉教カテリナ車輪>と、花束をお土産にいただいた。そのままふらふらしていると、光原百合さんを発見。おひさしぶりです。
帰りがけに、松浦さんに「ちゃんと食べられましたか?」ときかれた。
チーズケーキいっこしか食べてません。
小心者のわたしは、あまりの緊張で、全然、食欲がなかったのだった。ここのお食事はおいしいって評判だから、楽しみにしてたのに。しくしく。
帰宅後。27枚撮りの使い捨てカメラの、残り26枚のフィルムをどうやって消費しようかと悩みつつ、就寝したのでありました。
うわー、なつかしいですねー。なさけないですねー。
島田さんとの写真を撮ってくださったのは、通りすがりのプロカメラマンの本多正一さんで、「あの本多さんに<写ルンです>を渡したのかい」と、あとで友達にさんざんバカにされました。
たしかにちょっとかっこ悪かったかも、と反省したわたしは、今年のパーティーには、妹のカメラを取り上げて、持って行きました。でも、まだフィルムが残ってるから、現像してないのよう。文士劇観劇れぽーと 4年前に、今は亡き「有楽町そごう」七階の劇場でもよおされた、推理作家協会による文士劇の観劇レポートです。これもまた、創元推理倶楽部通信からの再録です。
「中村さん、そういえばずっと前に、文士劇に行きたいと言っていましたよね? 編集部のチケットがありますから、よければ・・」
「行きます」
どうやら松浦さんのものだったらしいチケットをとりあげて、わたしは文士劇に行ける事になった。しかも、ひとりで行くのはいやだと駄々をこねて、友達の分までせしめてしまった。
ああ、松浦さんって、ときどき本当にたまにはとってもいいひとだわ。
「そのかわり、強制ではないんですが、通信にのせるレポートを書いてくださいませんか。強制ではないんですけどね、もし、むこうで創元推理倶楽部のメンバーにあったら、その人たちにもお願いできればありがたいんですが。あ、全然、強制じゃありませんから」この文士劇のチケットは、全国のチケットぴあなどで発売開始とほとんど同時に完売になってしまったものだが、こうして、公演の四日前に突然、行けることになってしまった。
さて、公演当日。有楽町そごうに五時に到着。友達との待ち合わせが五時半なので、ぶらぶらとそごうの中を歩く。すでにデパート内の客層がいつもと違う。なんというか、いかにも神保町にいそうなオーラを放つ人々ばかりなのだ。みんな、三省堂の袋なんかぶらさげちゃってるし。
五時十五分に友達と合流。「ちょっと早めだけど、そろそろ並ぼうか」と、そごう七階にあるよみうりホールに向かう。
しかし、ちょっと早め、とか、そういう次元の話ではなかった。
なにしろ全席自由なので、気合いのはいった人々が、午前中から並んでいたらしいのだ。スタッフが慌てて作ったとひとめでわかる、いかにも手作りっぽい整理券も、昼にはくばりきってしまったとか。
まさか立ち見じゃないだろうな。
七階には行列をつくるスペースがないので、階段にぞろぞろと並ぶことになった。わたしたちは整理券のない組なので、整理券を持った人々の隣の列に並んだ。整理券は300枚(らしい)。ということは、わたしたちがはいれるころには、すでに300人がはいったあとなのね、とめまいを起こす。
六時十五分に列が動き出すまでの一時間、わたしはまわりを観察することでヒマをつぶした。ここに来るまでは、偏ったひとばかりだったらこわい、などと思っていたのだが、眼の前は子連れのお父さんだし、うしろにいるのは穏やかそうな老夫婦だし、とわりに普通の人ばかりのようでひとまず安心。
しかし、一時間もたてばいろいろある。なにしろものすごい人いきれで、狭い階段はとんでもない暑さになった。しかも立ち通し。ついに、うしろに立っている穏やかそうな老夫婦が怒りだした。こわい。
そのうちに、小さめのスケッチブックをかかげた女性が階段をおりてきた。スケッチブックには「チケットをゆずってください」の文字とイラストが。ええー、そんなもん、あるわけないじゃん、と思っていたら、なんと。眼の前の子連れお父さんが、「あ、チケットありますよ」といきなり財布を取り出した。そ、そうかー、ダフ屋経由でなくても、チケットって、定価で手にはいるものなのか。貴重な裏ワザを覚えた。
長い待ち時間のあと、ようやく中に入れてもらうと、入り口でパンフレットと出演者たちのサイン本(各自違います)を一冊いただいた。わたしはあまり作家さんのお顔を知らないので、さきにパンフで顔と名前と配役を覚えよう、と考えていたのだが、すでに開演時刻をまわっていたので、席を確保して、飲み物を調達して、やれやれと思った三十秒後に場内が暗くなった。
観に来た人々のほとんどに、お目当ての出演者がいたと思うが、わたしにはナマの山口雅也さんを見るという野望を持っていた。山口さんはキッドの役で出てくるんじゃないか、あの髪ならパンクをやれる、と、なんか違う意味でひどく期待していた。ああ、それなのに。・・でも、あの役も妙にはまっていて、おもしろかった。
しょっぱなから、客席は爆笑の嵐。司会進行兼プロンプター兼人物紹介役のシンポ教授がときどき芝居をとめて、舞台のすみっこで、弁士のごとく、出演者を紹介してくれるので、パンフレットを予習しなくても大丈夫だった事が判明する。
客席は終始、いい雰囲気だった。特定の人気作家ばかりにやたらと歓声があがることはなく、みんなが純粋に、作家さんたちの一生懸命な姿に大喜びして、夢中で手をたたいていた。
ところで、舞台の上はすごいことになっていた。演技上の基本的な注意事項を忘れる出演者たちに、基本を思い出させるシンポ教授。台本を堂々と朗読する人。手のひらにかくしきれていないカンペを読み上げる人。いさぎよくセリフを忘れた事を宣言する人、数名。プロンプトするシンポ教授。
ヌンチャクをふりまわすマニア。拳銃の考証がなっていないと講釈をするマニア。華麗なガンさばきを披露し、投げ上げた拳銃を受け取ろうとして、おっことすマニア。なんとかアドリブでまとめるシンポ教授。
おもむろに奇術を始める紳士。スキップしてターンする紳士。発砲スチロールのテレビカメラを重たげにかついで走り回る美女。妙にかわいらしい声の少年。異様に野太い声の淑女。基本的な注意事項を、何度も出演者たちに思い出させるシンポ教授。
「猫大好きフリスキー」を片手に、逃げた名探偵を探す作家。携帯電話で、持ちキャラの名探偵を本気で呼び出す作家。必死に軌道修正をするシンポ教授。
スタジャンのデザインをしたものの、年号を間違って作ってしまった(実話です)黒手袋の幽霊。とびまわる怪盗。よれよれのシンポ教授。
フラメンコ。駄洒落。ぬいぐるみ。着ぐるみ。
よし、これだけ書いておけば、正確な内容紹介になってるでしょ。
ほんとにこーゆーお芝居だったんだってば。舞台が終わったあと、こんなに楽しい企画なのだから、ぜひぜひ毎年恒例にしてほしい、と書いて、わたしたちはアンケートを提出した。
うん、本当に恒例になるといいなあ。いやー、なつかしいですねー。まさか「有楽町そごう」がなくなるとは思いませんでしたねー。あそこはけっこう穴場だったんですよ、場所柄、おもちゃがなかなか売れなくてねえ、ドラクエとか、発売当日の夕方にふらっと寄って、簡単に入手できるという・・こらこら。
浅羽莢子さんの演技が、まるで本物の女優さんのようだったので、わたしと友達は、「やっぱり舞台経験のある人はうまいわあ」などとしきりに感心していました。
ないそうです。
北村薫さんはとってもお茶目で、かわいー、という声があがっていました。たしかにラブリーでした。